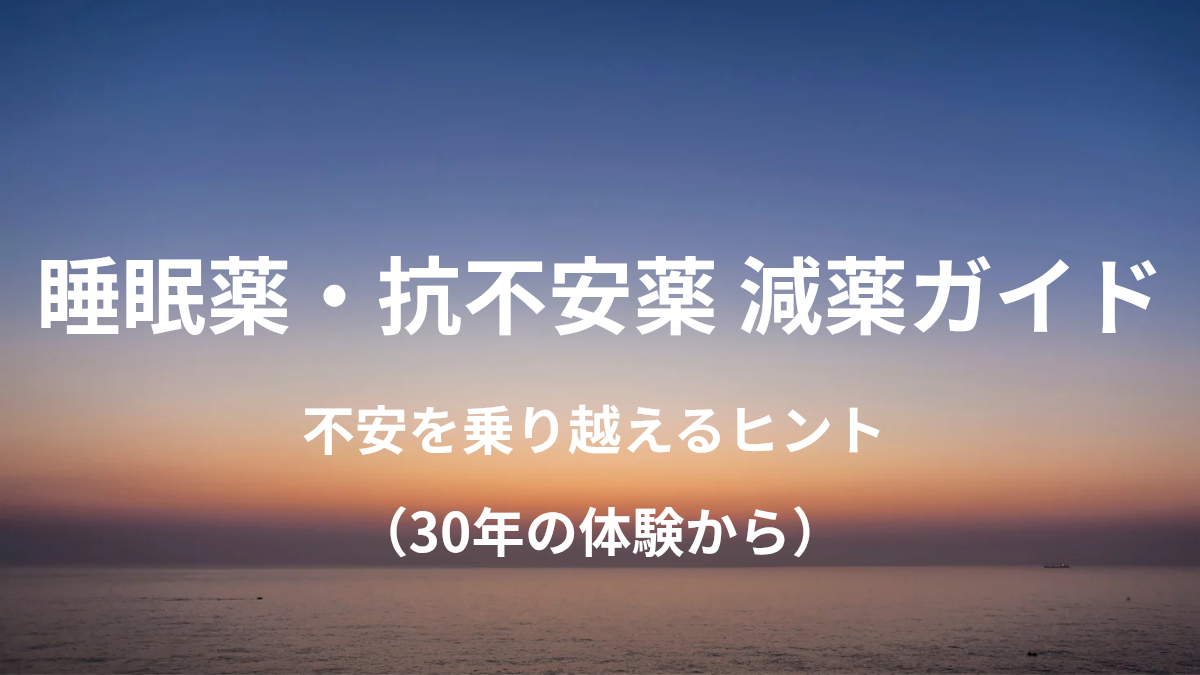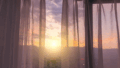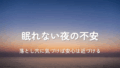「睡眠薬を減らしたいけれど、不安でいっぱい」「眠れない夜が続くのが怖い」──。
これは不眠に悩む人なら誰もが抱く思いだと思います。
私自身も、長いあいだ薬に頼り続け、減薬を考えたときは大きな恐怖と不安を感じました。
それでも少しずつ取り組み、専門家に支えてもらいながら試行錯誤を重ね、今では薬なしで眠れる日が増えています。
この記事では、その過程で学んだ減薬の流れと工夫を整理しました。
初めて減薬に挑む方や、今まさに不安の中にいる方が、道しるべのように使える内容になっています。
減薬を始める前に(準備期)
専門家と一緒に進めること
「薬を減らしたい、でも眠れなくなったらどうしよう」
これは不眠症の人なら誰もが抱く不安だと思います。
私自身も30年近く薬に頼り続けてきました。睡眠薬だけでなく、デパスという抗不安薬も処方されていて、「これなしでは眠れない・安心できない」と思い込んでいたのです。だから減薬を考えたときは恐怖でいっぱいでした。
そこでまず伝えたいのは――減薬は必ず専門家と一緒に進めることです。私は不眠相談員と主治医、両方に確認をしてから取り組みました。
そしてそのうえで始めたのが、「いきなり薬を減らす」のではなく、**生活リズムや心の支えといった“土台を整える準備”**でした。
減薬を始める前の準備チェックリスト
減薬を始めるときに大切なのは、いきなり薬を減らすことではなく 「土台を整える」ことです。
次のような準備をしておくと、不安を和らげながら一歩を踏み出せます。
- ✔ 専門家に相談する
主治医や不眠相談員など、信頼できる伴走者を見つける。ひとりで抱え込まないことが安心につながります。 - ✔ 生活リズムを整える
毎朝同じ時間に起きる/朝日を浴びる/3食の時間をなるべく一定にする。体内時計を安定させることが減薬の下地になります。 - ✔ 安心できる行動を用意する
不安が強いときにできる「小さな行動」を決めておく(例:深呼吸、短い散歩、ノートに書く)。 - ✔ 支えになる人や習慣を持つ
信頼できる人に「減薬を始める」と伝える、カウンセリングやヨガなど心を整える習慣を取り入れる。 - ✔ 自分を励ます道具を用意する
ノートに「安心できる言葉」「これまで乗り越えたこと」を書き溜めておくと、後で見返したときに支えになります。
行動チェック(準備期)
- 起床時間を固定する(眠れなくても毎朝同じ時間に起きる)
- 質の良い朝食を食べる(卵・納豆・バナナなどセロトニンの材料を意識)
- 日中はなるべく活動する(やる気を行動に変えて体を疲れさせる)
- 眠れない時は布団から出る(ベッド=眠れない場所にしない)
- 夜は照明を落とす(メラトニンを出やすくするため)
【まとめリンク】
減薬初期に出やすい不安と体の変化
「眠れるかな」という恐怖
減薬初期は毎晩「今日は眠れるかな」「不安が出たらどうしよう」と恐怖でいっぱいでした。
眠れないまま朝を迎えると、「このまま一生、薬なしでは眠れないのでは?」という絶望感に襲われ、昼間も頭がぼんやりして人と話すのもつらく、仕事も思うように進まない日が続きました。
でも今振り返れば、減薬初期に強い不安や眠れない夜が増えるのは**“想定内”**。
大切なのは「不安をゼロにすること」ではなく、「不安と付き合う工夫」を持つことだと実感しました。
体に現れる変化とケア方法
さらに、眠れない日が続くと「体の痛み」が出ることにも驚きました。肩や腰の重さ、全身のだるさ…。
不安と不眠が続くことで自律神経が乱れ、体に不調が現れるのは自然なことだそうです。
私はヨガで体をほぐしたり、鍼治療やマイクロカレント(微弱電流治療)を取り入れることで、少しずつ体のつらさを軽くしていきました。
小さなケアを積み重ねることで、**「眠れなくても体をいたわることはできる」**と思えるようになり、不安に押しつぶされずにすみました。
行動チェック(減薬初期に意識したこと)
- 👉 時計を見ない
夜中に時間を見ると「あと何時間しかない」と焦りが強まります。(私は時計を隠しました) - 👉 不安を紙に書き出す
眠れない夜ほど“書いて外に出す”ことで心が軽くなります。
詳しいやり方は体験記事にまとめています →下部の【まとめリンク】をご参照ください。 - 👉 夜のルーティンを決める
毎晩同じことをするだけで、脳が「眠りの合図」と覚えてくれます。(例:読書・呼吸法・アロマ)
【まとめリンク】
📌 関連記事はこちら
👉 減薬中の眠れない日々──私を支えたのは「生活リズム」 “減薬中の眠れない日々──私を支えたのは「生活リズム」” ‹ 眠りと心を整える実践ガイド
👉 減薬と不安への向き合い方|デパスを手放した私の実体験 “減薬と不安への向き合い方|デパスを手放した私の実体験” ‹ 眠りと心を整える実践ガイド
💡 補足
私は不眠相談員から「認知行動療法(CBT)」を勧められました。不安や考えを整理する方法として知られています。興味のある方は参考になるページをご覧ください。
👉 ストレスに強くなるライフスタイル(外部リンク)ストレスに強くなるライフスタイル
減薬の停滞期にぶつかったとき
生活習慣だけでは進めなかった私
減薬を始めてしばらく経ち、生活リズムや運動などの習慣はある程度身についていました。
それでも夜になると「眠れなかったらどうしよう」という不安が強くなり、気持ちが揺れやすい日が続きました。
「これ以上は進めないのでは…」
「また振り出しに戻ってしまうのでは…」
そんな思いが募り、足が止まってしまったのです。
この“停滞期”は、努力してきたからこそぶつかる壁だと思います。けれど、当時の私はそれを「失敗」と捉えてしまい、焦りが強くなっていました。
カウンセリングで見えた“心の仕組み”
停滞を抜け出すために私が選んだのが、カウンセリングでした。
生活習慣を整えるだけでは夜の不安が消えず、「根本から原因を見直さないと進めない」と思ったからです。
カウンセリングでは、ただ話をするだけではなく、自分の“心臓部”を見せられているような感覚がありました。
そこで一番心に響いたのは、次の二つです。
- 「○○しなければならない」という縛りを緩めましょう
- 他人の期待ではなく、自分を真ん中に置きましょう
この言葉が腑に落ちた瞬間、肩の力がふっと抜けて、心が軽くなるのを感じました。
「頑張らなければ」と自分を追い込むのではなく、「そのままの自分で大丈夫」と思えるだけで、不眠への恐怖も和らいでいったのです。
停滞期を乗り越える工夫
減薬はまっすぐには進みません。眠れない夜や不安が強まる時期もあれば、急に眠れるようになる時期もあります。
👉 大事なのは「停滞=失敗ではない」と理解すること。
私自身も、焦って薬を戻すのではなく、整えてきた生活リズムや運動の習慣を続けるようにしました。
また、不眠相談員や主治医と話すことで「このままで大丈夫」と背中を押してもらえたことも安心につながりました。
停滞期は壁ではなく、次に進むためのプロセス。
焦らずに続けること、そして心のケアや伴走者の存在を取り入れることが、乗り越えるための大きな助けになります。
行動チェック(停滞期に意識したこと)
👉 スケジュールを柔軟にする
事前に細かく決めすぎず、体調や眠りの様子に合わせて調整する。
👉 不調が強いときは立ち止まる
不安や不眠がひどいときは、いったん元の量に戻してもOK。「続けられる形」を保つことが大切。
👉 少しずつ細かく減らす
一度に大きく減らすのではなく、小さな単位で少しずつ進める方が安心。
👉 波があると理解する
眠りの質が下がる時期や、逆に上がる時期があります。その波は自然なプロセスです。
安定期を保つコツ
減薬が進むと、不安や不眠が和らぎ「少し楽になった」と感じられる安定期が訪れます。
👉 この時期に大事なのは、油断せず「安定を長く保つ工夫」を続けることです
行動チェック(安定期)
- 規則正しいリズムを守る
眠れるようになっても、毎朝同じ時間に起きる・朝の光を浴びる習慣は崩さない。 - 生活と運動の土台を維持する
調子が良くても食事や睡眠リズム、リラックス習慣はそのまま。 - 人とのつながりを少しずつ広げる
眠れる日が増えると、人との約束もストレスになりにくくなる。 - 心を緩める時間を持つ
心理学の本や動画を見て気づきを得たり、自分を振り返る内省の時間を持つ。
私の体験
眠れる日が増えてくると、朝の目覚めから違いました。
「ちゃんと眠れた」という実感があると、疲れの取れ方がまるで違って、日中の行動範囲も自然に広がっていきました。
「また外に出てみよう」「人と会ってみよう」と思えるようになったのです。
調子が良いときこそルーティンを崩さないように意識しながら、ウォーキングや筋トレで体を動かし、心理学の動画を見て心を緩めることも取り入れていました。
快適に過ごせる日が増えると、自分の「やりたいこと」が自然に出てきて、その時間がさらに安定を支えてくれました。
減薬を完了して見えた景色
減薬を終えて振り返ると、その道のりは決して一直線ではありませんでした。
進んだと思ったら戻ることもあり、その繰り返しでした。
でも、根気よく続けることが大切で、「頑張りすぎない」ことも同じくらい大切だと気づきました。
眠りには力ではなくリラックスが必要です。
ある程度「薬を飲めば眠れる」という状態になったら、今度は“心地よい時間”を意識して生活することが、次のステップにつながります。
私の歩んだ過程
私の場合、最初は薬を飲んでも眠れない日々からのスタートでした。
そこから少しずつ薬を減らし、薬を飲めば3〜4時間眠れるようになり、さらに生活習慣の工夫を重ねることで5〜6時間眠れる日も出てきました。
もちろん、眠れない夜が戻ってくることもありましたが、「波があるのが自然」と受け止められるようになったのです。
この経験を通して、薬を飲んでも眠れなかった私が、今は薬なしでも眠れる日が増えてきました。
これは「不可能ではない」という希望を示す証だと思っています。
減薬はゴールではなくスタート
減薬を終えたとき、見える世界はまったく違いました。
それは“ゴール”ではなく、“新しい生活のスタート”。
自分の心や体と向き合う習慣が根づき、薬に頼らなくても眠りと共存できる感覚を持てるようになったのです。
薬を手放すことは、眠りの自由だけでなく、自分の人生を取り戻すことにつながっていました。
よくある質問(FAQ)
Q. 運動はどのくらいすればいいですか?
A. 激しい運動でなくても大丈夫です。散歩や軽い筋トレなど「心地よい疲労」を積み重ねることが、夜の眠りをサポートします。
Q. 人付き合いがストレスになったら?
A. 無理に広げる必要はありません。安心できる人との関係を保つだけで十分です。調子が整ってきたら、少しずつ外のつながりを広げてみましょう。
Q. 減薬中に気持ちが落ち込むときはどうしたらいいですか?
A. 私の場合、大きく2つの方法がありました。
- 感情を掘り下げる
「なぜ今こんな気持ちになっているのか?」をノートに書き出して整理します。感情の正体が見えるだけで、不安が少し軽くなります。 - とにかく行動する
考え込むより動く。外を5分歩く、部屋を片づける、お皿を洗う──そんな小さなことでも「動けば気持ちも少し動く」感覚がありました。
気持ちに向き合う方法と、気持ちから離れる方法。どちらも場面によって助けになりました。
Q. 家族や大切な人にはどう伝えればいいですか?
A. 減薬は一人で抱え込むと不安が強くなります。私も夫に「今こういう取り組みをしている」と伝えたことで、支えになりました。
すべてを詳しく話す必要はありません。「少しずつ薬を減らしているから、不安になる日もあるかもしれない」と一言共有するだけでも安心につながります。
信頼できる相手に理解してもらえることは、減薬を続ける大きな力になります。
著者プロフィール&免責
- 著者:りり(30年以上の不眠経験。現在はほぼ無投薬で睡眠)
- 免責:この記事は私の経験をもとにした一般情報です。医療判断は必ず主治医とご相談ください。