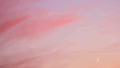「もう薬がないと眠れないかもしれない」――
そんな不安の中にいた私が、少しずつ変わりはじめたきっかけのひとつが、意外にも腸を整えることでした。
もちろん、腸活だけで劇的に改善したわけではありません。
でも、腸の状態を意識することで、心や睡眠にもじわじわと良い変化が起きてきたように感じたのです。
このブログは、かつての私のように
「眠れない夜が続いてつらい」
「薬に頼らずなんとかしたい」
そう思っている方に向けて書いています。
🌿 腸と心はつながっている
腸は“第二の脳”とも呼ばれるほど、心の状態と密接に関係しています。
腸内で作られる神経伝達物質セロトニンは、心の安定や睡眠にも深く関わるホルモン。
腸の調子が良いとき、人は自然と気分が落ち着き、ストレスにも強くなります。
私も以前は「腸のことなんて気にしたことがない」というタイプでした。
けれど、睡眠の勉強をする中で、腸が心にも眠りにも影響していることを知り、意識が変わりました。
🧠 腸内環境が乱れると、眠りにどんな影響が出るの?
腸の状態は、心だけでなく眠りのリズムにも深く関係しています。
最近の研究では、腸内環境が乱れることで次のような悪影響が起こることが分かってきています。
- セロトニンとメラトニンの流れが乱れる
腸は「第二の脳」と呼ばれるように、体内のセロトニンの約90%を作り出しています。
セロトニンは夜になると睡眠ホルモンのメラトニンへと変化しますが、
腸内環境が乱れるとそのリズムが崩れ、入眠しにくくなると考えられています。 - 炎症やストレスホルモンが増えて眠りが浅くなる
腸のバリア機能が弱まると、炎症性物質が血流を通じて体全体に広がり、
ストレスホルモン(コルチゾール)が過剰に分泌されやすくなります。
その結果、夜になっても神経が高ぶり、眠りが浅くなる傾向があります。 - 自律神経のバランスが崩れる
腸と脳は腸脳相関と呼ばれるネットワークでつながっています。
腸が不調になると、その信号が脳へ伝わり、交感神経(緊張モード)が優位になりやすくなります。
この状態が続くと、夜にリラックスしにくくなり、寝つきに影響します。
つまり、腸内環境の乱れは「ホルモン」「炎症」「自律神経」という3つの方向から、眠りの質を下げてしまう可能性があります。
反対に、腸を整えることは眠りのリズムを内側から支えるケアにもなります。
📚 参考文献・出典
- Frontiers in Neuroscience (2020). The gut microbiome and sleep: Links and potential mechanisms.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.00044/full - PLoS ONE (2019). Association between sleep and gut microbiome composition in humans.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222394 - 日本睡眠学会・日本腸内フローラ学会 共同研究レビュー (2022)「腸脳相関と睡眠:腸内環境の変化が睡眠の質に与える影響」 (日本睡眠学会抄録集より要約)
※本記事は公的機関および査読付き学術誌の情報をもとに作成しています。
内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、医療行為や診断を代替するものではありません。
🍎 私が続けている小さな腸ケア
- 🥣 味噌汁に根菜や海藻を入れる(ごぼう・にんじん・大根・わかめなど)
- 🍎 朝にフルーツを食べる(キウイ・バナナ・りんご)
- 🍚 白米にもち麦や雑穀を混ぜる
- 🫘 豆類や海藻を副菜にプラス
- 💊 必要に応じて整腸サプリ(例:ビオスリー)を取り入れる
これらを続けていると、
理由のない不安が少しずつ和らぎ、心の焦りが減っていくのを感じました。
腸を整えることは、心と体の「静かなチューニング」なのかもしれません。
💡 体の内側から眠りを育てる
眠りを整えるためには、夜だけでなく1日のリズム全体を意識することが大切です。
朝は光と朝食で体内時計をリセットし、夜は体を温めてゆるめる。
腸の調子が整えば、心も体も自然と安心を取り戻していきます。
「腸を整える」という行動は、実は“心と眠りの土台を整えること”。
完璧にやろうとせず、できる範囲で続けることがいちばんの近道です。
🕊関連記事:
・💫体から整える(Body Navi)
・🧠脳から整える(Brain Navi)