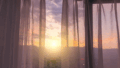※この記事は、「今日は仕事に行く」または「行かざるを得ない」と決めた方に向けた内容です。
もし、まだ「休むか・行くか」で迷っている場合は、先にこちらの記事で今日の判断を整理してください。
→ 仕事は休むべき?判断できないときの“今日の状態”の見極め方
はじめに|眠れない日の仕事は「100%を目指さない」
眠れなかった朝、仕事に行くと決めただけで、すでにかなりのエネルギーを使っています。
そんな日に
「いつも通りやらなきゃ」
「迷惑をかけないように頑張らなきゃ」
と自分を追い込むと、心身の消耗は一気に大きくなります。
眠れない日の仕事は、
うまくやる日ではなく、ダメージを最小限にする日。
今日はそれで十分です。
今日の基本方針|“低速運転モード”でいく
眠れない日は、集中力・判断力・記憶力が落ちやすい状態です。
だからこそ、最初にこう決めてしまいます。
「今日は50%運転でOK」
これは甘えではなく、
事故やミス、後の大きな不調を防ぐための現実的な判断です。
眠れない日の仕事・具体的な乗り切りポイント
そのまま使える形でまとめます。
- 今日は「最低限やること」だけに絞る
- 午前中だけ集中、午後は流す
- 判断はメモに書いて“外部脳”に任せる
- 仮眠は10〜20分まで(長すぎると逆効果)
- カフェインは朝に1杯まで
- 危険作業・重要判断は可能なら避ける/一言相談する
眠れない日は、
作業量を減らす > 根性で乗り切る
この優先順位が、あとから効いてきます。
うまくいかなくても「それでいい」
眠れない日の仕事では、
- 思ったより進まない
- ミスが増える
- 人の言葉に敏感になる
こうしたことが起こりやすくなります。
それは能力や姿勢の問題ではなく、
脳が十分に休めていない状態だから。
今日は評価しない日。
反省もしない日。
「出勤した」「時間を過ごした」だけで合格です。
帰宅後にやっておきたいこと(回復を遅らせないために)
仕事を終えたら、次のことだけ意識してください。
- 今日を振り返らない
- できなかったことを数えない
- 「今日は低速の日だった」と言葉で区切る
眠れなかった日の回復は、
その日の夜をどう過ごすかで変わります。
今日を責めずに終わらせることが、
次につながるいちばんのケアです。
まとめ
- 眠れなかった日は「低速運転」で十分
- 100%を目指さない方が、結果的に回復が早い
- 今日は評価しない・反省しない
- 乗り切った自分を、最低限守る日
もし、
「本当は休んだほうがよかったのでは」
という迷いが残るときは、
改めて今日の状態を整理してみてください。
→ 仕事は休むべき?判断できないときの“今日の状態”の見極め方
免責
本記事は筆者の体験と一般的な知見に基づく情報提供です。
医療判断・治療・投薬の調整は必ず主治医や専門家と相談してください。