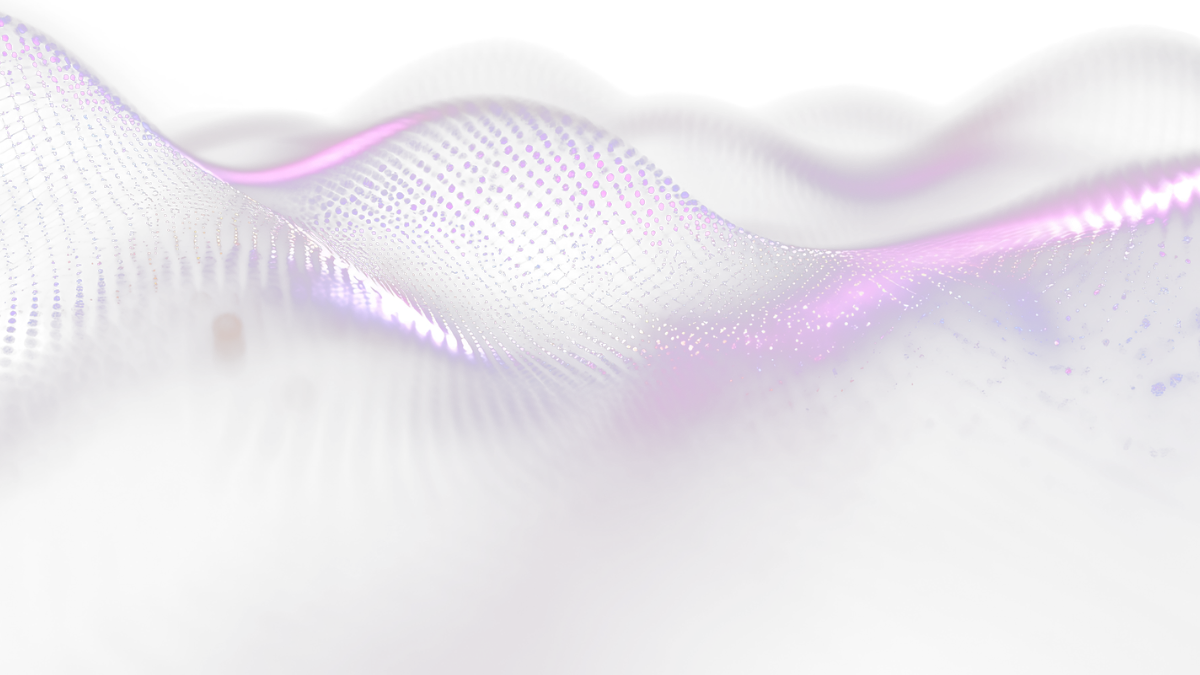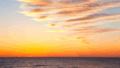眠れない夜、「〇〇すべき」と自分を縛っていませんか?
「眠れない夜はスマホやテレビを見てはいけない」──そんな“すべきルール”を真面目に守っていませんか?
私も長年、不眠に悩む中でこのルールを信じ込み、必死に守っていました。
眠れない夜、布団から出て本を読む。
それ以外の選択肢は「そうすべき」と思い込み、自分に許していなかったのです。
けれど、本を開いても気持ちは落ち着かず、結局「今日も眠れなかった」と自分を責めてしまう日々。
ルールを守れば守るほど、眠りは遠ざかっていきました。
スマホやテレビを見てはいけない──“すべきルール”の罠
「スマホは見ちゃいけない」「本を読むべき」──そんな“すべきルール”が、かえって心を緊張させていました。
私は「眠るための正しいやり方」を必死に探していたのに、それが逆に不安を増やしていたのです。
「ちゃんと眠れなかった自分はダメ」と感じるたび、心と体がどんどん固くなっていきました。
ルールを真面目に守るほど、眠れなくなる理由
「ルールを守っているのに眠れない」。
そんなとき、実は脳が“努力モード”に入っています。
完璧に眠ろうとするほど、交感神経が優位になり、体はリラックスできなくなる。
眠りは本来、生理現象。努力してつかむものではありません。
“こうすべき”と思い込むほど、脳が緊張し、眠りを遠ざけてしまうのです。
「〜すべき」「〜しなければ」に気づいた夜
そんな私に転機をくれたのが、カウンセリングでの先生の言葉でした。
「なんで、テレビくらい見たっていいんですよ」
その一言に私は驚きました。
これまで必死に守ってきた“すべきルール”が一気に崩れていくような感覚でした。
先生は続けて、
「“〜すべき”“〜しなければ”というルールが多すぎて、自分の本当のしたいことを置き去りにしていませんか?」
と問いかけてくれました。
確かに、スマホで人とやりとりを始めると頭が冴えてしまいます。
それは避けた方がいい。
けれど、好きな音楽を聴いたり、YouTubeを見て気分が良くなるなら、それだって眠るための大切な時間になるんですよ、と教わったのです。
不安が眠りを遠ざける脳の仕組み
ある夜、私は好きなYouTubeに夢中になり、気づけば「眠れなかったらどうしよう」という不安をすっかり忘れていました。
楽しくて仕方なく、そのまま自然に眠れたのです。
そのとき初めて、「あれ、頑張って眠ろうとしないほうが、案外うまくいくのかもしれない」と気づきました。
この不思議な現象には、脳の仕組みが関係しています。
脳は同時に二つのことに強く集中することができません。
不安に意識を向ければ眠れなくなりますが、楽しいことに没頭すると、不安を処理する余力がなくなり、自然と薄れていきます。
さらに、好きなことを楽しむ時間は、脳内でドーパミンやセロトニンといった「安心」や「リラックス」をもたらす物質を分泌し、心と体を穏やかに整えてくれるのです。
真面目さと“すべき思考”が不眠を悪化させる理由
不眠に悩む人ほど真面目で、完璧思考の傾向があります。
「こうしなければ眠れない」「これをしてはいけない」とルールを積み重ねることで、かえって心が固くなり、眠れなくなってしまうのです。
眠りは本来、努力でつかみ取るものではありません。
むしろ「眠れなきゃ」と頑張るほど、眠りは逃げていきます。
まとめ|“すべき”を緩めた瞬間、心は眠りに近づく
カウンセリングを通して気づいたのは、「正しいルールを守ること」よりも「気楽さを持つこと」の方がずっと大切だということでした。
眠りは努力で手に入れるものではなく、心と体が自然にゆるんだときに訪れるもの。
だからこそ、まずは自分を締めつけている“すべきルール”を少しずつ緩めていくことが大きな一歩になります。
とはいえ、「眠れなくてもいい」と思うのは、言葉で言うほど簡単ではありません。
眠れない夜の苦しさを知っているからこそ、きれいごとに聞こえてしまうのも当然です。
でも、そこが実は不眠から回復していくうえでの重要な転換点なんです。
眠れないことそのものより、「眠れなかったらどうしよう」「眠れないと明日がつらい」「眠れない自分はダメだ」という思考が、不眠をこじらせてしまう。
じつはこの“思考に支配されること”こそ、眠れない夜の本当の原因につながっていました。
▶「眠れない夜の本当の原因|考えに支配されていた自分に気づいた日」
(考えに飲み込まれる仕組みを、体験を交えて書いた記事です)
この思考を少しずつゆるめていくことが、回復の本質です。
いきなり完璧に思えなくてもかまいません。
まずは「眠れなくて不安なのも無理ないよね」と、自分の気持ちを否定せずに受け止めるところから始めてみてください。
そんな小さな一歩が、心を軽くし、眠りへの道を自然に導いてくれます。